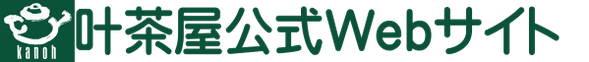「叶茶屋」店主のよもやま話
1.当店の電話番号
A温泉旅館(4126:良い風呂)、B茶通販社(59-0141ゴックンおいしい)など、店名・社業と電話番号を、語呂合わせで一緒に覚えてもらおうとしている店や会社は、結構あります。
しかし、一度“電話帳”に登録してしまえば、次からはその都度数字ボタンを押さずに掛けられるのが、今のスマホ(携帯電話)。
だとすると、「商売屋の電話番号は、語呂合わせ等で覚えてもらうために、出来るだけ分かりやすいものを」という理屈は、“電話帳”機能が無かった頃の(固定電話が主流だった時代の)名残りなのでしょうか?
当店の電話番号の下4桁は2783、覚えにくい4数字の配列です。(↑写真 : 1975年頃使用していた便箋に印刷されていたもの)
〈ちなみに、2本目の電話番号7120は、現在FAXに使用しています。〉
何故わざわざ、このような電話番号を選んだのでしょうか?
答えは、当店創業(1948年)当時の電話回線事情にありました。
以下は、私の父である先代社長から聞いた話です。
「創業して、まず必要になったのは電話(電話番号)だった。
でも当時は、簡単に電話を引ける時代ではなかった。」
「電話債券を購入しなければならず、購入に多大な費用がかかることもさることながら、
市内局番というものがなかった時代で、静岡市の電電公社(NTT の前身で公営企業)には交換機が1台あるのみ。
当然電話番号は有限で、電話を持ちたくてもどこかの店が手放してくれないと入手できなかった。」
「加入予約してから延々と待たされ、待ちくたびれ、諦めかけた頃、『2783という番号が空きました』と電話局から連絡があった。
気が短く、既にしびれを切らしていた祖父は、『番号はなんでも良い。早く申し込め。』
その一言で、『静岡局2783』は、加納茂三郎商店の電話番号になった。」
また後から聞いたことですが、2783番を手放してくれたのは、祖母がよく買い物をしていたK陶器店。
静岡市内の繁華街のひとつ、七間町にある繁盛店でした。
「覚えやすい番号に替えることができたので、2783番は必要なくなった」というのが、その理由のようでした。
時代は流れ、静岡に市外局番「2」局ができ、それが「52」局、「252」局にかわっていきました。
替えようと思えばチャンスは何度もあったはずなのに、父も私も2783番をやめませんでした。
きっと使っていくうちに、この4桁に愛着が湧き、「気がついてみたら手放せなくなった」
10年位前に、どこかで頂いたお菓子の、包装紙に書いてあった店の電話番号に眼が止まりました。
「2784」、「ウチと1番違いだ。」
「ここもその昔、待ち切れなくて取った番号なのかな?」
でも、店名が船橋屋とあって納得しました。
たかが電話番号、されど電話番号です。

「叶茶屋」店主のよもやま話
2.店名、社名
現社名の「成茶加納 (せいちゃかのう)株式会社」は、1991(平成3)年3月1日に、それまでの社名、「株式会社 加納茂三郎商店」を変更してスタートしました。
早いもので、2021年に創立30周年を迎えました。
保守的な茶業界にあって、社名・店名を変えるなどはあり得ないことに等しかったようで、当時は内外からいろいろなことを言われました。
「えっ?これって『なりちゃ』って読むの!」と茶化されたり、
「製茶加納じゃないの?」と誤字と思われて指摘されたり、
「創業者の名前を外すなんて、言語同断!」と非難されたり。
先代社長の父が、1987(昭和62)年末に急逝し、私は弱冠30歳で代表者になりました。
周囲の助言もあり、「父親から息子にバトンタッチしても経営方針は変わっていない」ということをわかってもらうために、三年間は新しいこと(改革)を極力慎みました。
ただその間に、取引先の新規開拓にも励みましたが、訪問先で名刺交換をすると必ず言われたのが、「伝統のある静岡市のお茶屋っていうのはわかるが、社名を聞いて何を扱っているのかわからないのはマイナスだね。」でした。
当時は、合併や業態変更を機にCI(コーポレート・アイデンティティ)を導入する企業が多かったように記憶しています。
しかし同時に、単にカッコいい字体やロゴマークを導入しただけで、中身はほとんど変わっていないと感じる会社もありました。
私は業界内外の先輩達から意見を聞きながら、①社名は記憶に残る、漢字4文字以内。②苗字の加納は残す。③業種である茶を入れる を軸にすることにしました。
それに基づいて、コピーライターに社名を、デザイナーにシンボルマークを依頼しました。
上がって来た候補名を社員の意見や要望も参考にして検討を重ね、新社名は「成茶加納」に決めました。
頭の「成」は字画が少なくて書きやすいと思いましたが、最終的には創業者である祖父・茂三郎の「茂」と同義語〈=しげる〉であったことが決め手となりました。
一方のシンボルマークは、簡便性の高い缶やペットボトルのドリンクの消費量が多くなっても、茶器を使って「美味しくお飲み下さい。」「安らぎや寛ぎのあるティータイムをお愉しみ下さい。」という思いを込めて、筆で急須を描いたもの(↑ 上記の写真)にしました。
社名を変更して直ぐに喜んでくれたのは、「電話で名乗る時に、セイチャカノウという社名を噛まないで言えるから」という営業スタッフの女性でした。
その後の名刺交換で、「『成』が印象に残るね。」 「一度覚えたら忘れない社名だね」と言われることが多くなり、あのタイミングで変更して良かったと思っています。
後日譚を一つ、今では検索で同一名が既に存在するかどうかは簡単に調べられますが、当時は今ほどインターネットが便利に使えず、しっかりと調べたつもりでも「ウチの社名と同名(類似名)だ」とクレームをつけられないかという心配がありました。
幸い、今に至るまでクレームをつけられたことはありませんでしたが、でももし「成」ではなく、候補の字の中にあった「精」を選んでいたら、岩手県一関市にある「精茶百年本舗」さんと類似社名になってしまうところでした。
「後から類似名をつけ、先方に不快な思いをして頂くことがなくて本当に良かった。」と、そのことを思い出すたびに胸を撫で下ろしています。

「叶茶屋」店主のよもやま話
3.店主4代
JR東海道本線、東海道新幹線、東名高速道路、国道150号線が並行して走り、日本坂トンネル等が貫く高草山(標高501m)。この静岡市と焼津市の境界にそびえる山の西側斜面には、今もまとまった茶畑があります。
初代・辰蔵(たつぞう)
その山麓にある集落、志太郡東益津村坂本(現・焼津市坂本)の一農家の次男に生まれた加納辰蔵は、明治時代の終わり頃、静岡市内に出て来て、茶の生産時期になると、実家や近隣の農家が作った荒茶を、静岡市内の茶問屋や再製業者に売って生計を立てた、お茶の仲買商人でした。(従って正確には店主ではありませんでした。)
現在の農協共販のような制度がなく、また取引補償が完備されていなかった時代でしたので、資金力の不十分な仲買商人の多くは、買取りではなく、茶農家から販売希望価格を聞いて荒茶を預かり、静岡市内の安西・茶町界隈の茶問屋や再製屋に売りに行きました。売った茶の代金回収をきちんと行える業者だという信用がなければ、農家はお茶を預けてくれません。
実家の父や兄がまじめに茶作りをしていたので、そこはクリアしていたのだと思います。
また辰蔵が主に扱う「志太のお茶」には、①静岡市近郊産地として認知されていて、茶問屋からの引き合いが強い。
②県内茶産地の中では(生産時期の早い)「平地・早場所(ひらち・はやばしょ)のお茶」だったので、茶問屋の仕入れ意欲が旺盛の(相場が下がらない)うちに生産が終わる。
と言う強みがあったはずで、欲をかかなければ商売としては決して悪くはなかったと思います。
やがて、隣村(現・焼津市関方)から、きく(旧姓・藤ヶ谷)を嫁に迎えた辰蔵は、坂本を出て静岡市内に居を構えます。
彼の茶仲買商としての仕事は、大半が生産時期の荒茶の売買でしたので、端境期には取引が無く(したがって収入も無く)、静岡市内で家族を養うために苦労も結構多かった ということは、容易に想像がつきます。
2代・茂三郎(もさぶろう)
辰蔵の長男・加納茂三郎(明治29年生)は、義務教育を終えた大正時代の初め頃、迷わずに茶に関わる仕事を選びました。
見習い期間を経て就いたのは、「茶問屋居付きの才取り(ゐづきのさいとり)」。今でいう個人事業主で、茶問屋の正規の店員ではありませんでした。
生産時期には、その店の主人や番頭さんに代わって、荒茶を売りに来る茶農家や仲買商と商談をしたり、旅のお客さん(静岡へ茶を仕入れに来ている地方の茶店店主や番頭)の代わりに茶農家や仲買商と商談したり、というのが主な業務でした。
商談が成立すると、「口銭(こうせん)」と呼ばれていた取引手数料をその労働対価として受け取っていました。
商いがないと収入を得られないのは辰蔵と同じですが、幸いなことに茶問屋の商いには茶が生産されていない端境期に、店同士で在庫茶の過不足を補い合う「業者間取引」が行われていました。その機会に商談を上手にまとめることができれば、安定した収入を得ることが可能でした。
大正12年、玉露で有名な志太郡朝比奈村近又(現・藤枝市岡部町玉取)の農家からヤヱ(旧姓・松野)を嫁に迎えました。
この写真は、正月、店の前にたたずむ茂三郎とヤヱ。(昭和43年<1968年>撮影)。
茶取引の実践の場で経験を積みながら、徐々にお茶鑑定の才覚を発揮するようになり、正規の店員に昇格しました。
当時勤めていた茶問屋は、静岡一(それはイコール全国一を意味する)の規模(取扱数量)を誇る大店(おおだな)でした。荒茶の仕入れを担当する店員は大勢いたようですが、「店が儲かるお茶を仕入れられる」「地方から仕入れにくるお茶屋さんに、たくさんお買い上げ頂き、しかも先方はそれが良いお茶だと大変喜んでいる」と、店の主人や番頭さんから評価してもらって、お給金も少しずつ増えていったようです。「それ(昇給)があったから、6人の子供を養い、学校に通わすこともできたんだよ」という話を、晩年のヤヱお婆さんから聞いたことがあります。
普段は温厚な人柄、「仏の茂三郎(モサ)」と呼ばれていましたが、お茶時期には別人(鬼)に変身するといわれていました。
それはある朝の商談でのこと、目に留まった(気に入った)お茶を、わずか何円かの違いで買い損ねた時には、「商いの成立しそうな値をおまえがおれにちゃんと伝えなかったから、今朝はひとっ葉も買えなかったじゃないか」と商談を持って来た才取り(斡旋屋)に大声で怒鳴り、怒りをぶつけたのでした。
判断が一秒遅れると、あるいは値を一円安くつけてしまうと、気に入ったお茶が買えない、その悔しさ、真剣勝負の厳しさをイヤというほど味わってきた、彼だからに違いありません。
3代・高一(こういち)
茂三郎の長男・加納高一(昭和2年生)は、6人兄弟(3男3女)の上から2番目として、静岡市内で生まれ育ちました。
4代・昌彦(まさひこ)

「叶茶屋」店主のよもやま話
4. お茶の運搬を担った「大八車」と「車力」
当店は、錦町の通りと茶町通りを南西から北東に結ぶ道の左側にあります。この道は、今(2020年)でこそ昭和通りのファミレスのデニーズ前の交差点から、7m幅で全長が約200mありますが、1960年代半ば(区画整理前)には、まだ軽三輪(オートバイに荷台をつけたような貨物車)が一台通れるかどうかという、道幅⒈5m程のいわゆる“路地”でした。
この路地は、茶町通りの裏通り(これもまた狭い道!)と交差していました。茶町通りに表玄関のある茶問屋や再製屋の裏口(荷の搬入・搬出口)は、この裏通りに面していましたので、茶最盛期の5〜6月には、当店の前を大海袋や大印籠(60〜80kgの茶が入ったのではないかと思われる大型の茶箱に詰めた茶を満載した、I運送店の大八車が往来していました。
この写真は、大印籠の蓋を取り、工場内で茶の一時保管に使っている駄櫃<だびつ>と呼んでいるもの。
高度経済成長期に入る前で、地方都市の個人事業者には自家用車(乗用車、トラック)を所有できる財力があったとは言えない時代でした。 ちなみに、当店には頑張って買った⁈ 中古のスバル・サンバー(360cc空冷エンジンの軽バン)があり、それが父の自慢でもありました。
エンジン付きの車が普及していないという理由で、茶の運搬も人力に頼らざるを得なかった時代だったことが、大八車を引く運搬職人に活躍の場を提供していたのかもしれません。
当時、市内には何軒かの運送店があったといいますが、残念ながら、まだ私は小学校にあがる前(幼稚園児)でしたので、鮮明で確かな記憶はありません。
木綿の丸首シャツ・地下足袋・ネジリ鉢巻の車力(しゃりき)と呼ばれた運搬職人が、重い荷を引くのに疲れたのか?、当店の前の路地に大八車を止め、キセルをくわえて“一服”していた姿だけは、60年近く経った今もはっきりと覚えています。
ちなみに、その時私の見た大八車と車力は終末期で、それからまもなく引退していきました。
さて祖父の話によれば、当時、平均的な車力は、
①500kg位の荷(茶)を積んだ大八車を一人で引いて、茶問屋や再製屋の工場を行ったり来たりしていた。
②この力仕事は、寿命を縮めてしまう程の重労働。加えて彼らの多くは、もらった給金を「飲む・打つ・買う」に注ぎ込み、「太く・短く・潔く」の生涯を送った人が多かった ようです。
その後I運送店は時代の流れに乗り、オート三輪(前輪が一つのトラックで、小型のダイハツ車や荷台の長い積載量が2トンのマツダ車があった)を導入して、静岡–東京間の茶の長距離輸送業務に進出していきました。
そして現在も、茶繁忙期にはこの店名をつけたトラックが、茶を積んで茶問屋街(茶問屋街)を行き来している姿を見かけることができます。
「叶茶屋」店主のよもやま話
5.お茶屋を支えた関連業種
成茶加納株式会社
9時~12時 13時~17時
〒420-0015
静岡県静岡市葵区錦町9番地
TEL 054-252-2783 / FAX 054-255-7120
e-mail: tea-meister@kanohchaya.com
叶茶屋(小売り部門)
10時~12時 13時30分~16時
〒420-0021
静岡市葵区茶町2丁目19-5
TEL 054-252-2783 / FAX 054-255-7120
e-mail: tea-meister@kanohchaya.com
小さいお店ですので、商品をご予約いただいてからご来店頂けると幸いです。
営業日:月曜~金曜
休業日:日曜・祝日
土曜日:新茶時期のみ営業
上記以外に年末年始休業・夏季休業有。